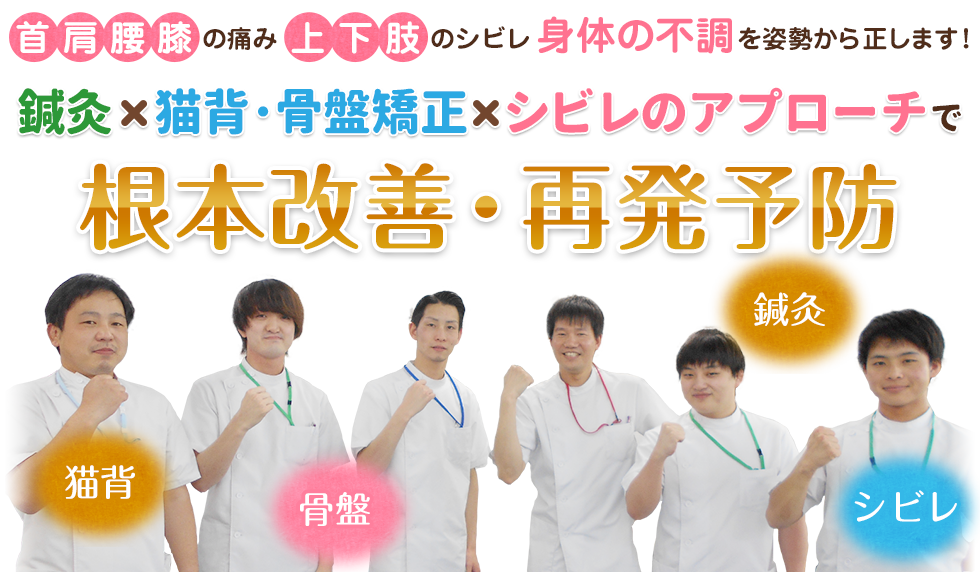
今回も引き続き消化器の診断に使われる用語の意味を紹介していきます(*^_^*)
○逆流性食道炎
胃液の食道への逆流により、食道粘膜が傷害された状態です。次の6つに分類されます。
①GradeN:内視鏡的に変化を認めないもの
②GradeM:色調変化型
③GradenA:長径が5mmを超えない粘膜傷害のあるもの
④GradenC:少なくとも1カ所の粘膜傷害は2条以上の粘膜ひだに連続して広がっているが、全周の3/4を超えないもの
⑤GradenD:全周の3/4以上にわたる粘膜障害
○食道アカラシア
食道と胃の接合部の筋肉の過度の収縮状態をいいます。筋肉の異常ですので、改善は見られません。内視鏡では診断がつかないことも多いのですが、上部消化管X線検査で診断が可能です。通過障害がひどくなると、食べ物が飲み込みにくくなる、吐いてしまうといったん症状が徐々に悪化します。一回の食事量は少なめにし、時間をかけて食べさせてあげてください。内服薬で症状を改善させる方法やn内視鏡的に狭い部分を拡張させる方法がありますが、一時的なことが多いので手術を行うことが多いです。
○食道炎
カビ、薬剤、胃液の逆流などにより、食道粘膜が赤くただれた病変です。
○食道外腫瘍
食道壁周囲の気管支などの臓器より発生した腫瘍です。
○食道潰瘍
食道に起こる限局性の組織欠損です。
○食道拡張
通常障害がひごくなると食べ物を飲み見込みにくくなる、吐いてしまうという症状が徐々に悪化します。通常障害の原因が、がんであることもあります。外部からの圧排であれば、それを確認するためにCTなどに追加検査が必要です。
○食道憩室
食道の壁が増殖し、内部に突出、もしくは変形している状態です。通常障害があると、吐き気、嘔吐や食べ物が飲み込みにくいなどの症状が現れます。内視鏡検査で腫瘍の状態や、良性か悪性かを検索する必要があります。
前回の続きを紹介したいと思います(^v^)
○粘膜ひだ集中
潰瘍の修復過程で、修復のために粘膜が集中してくるで、粘膜ひだの集中といいます。無症状ですが、潰瘍をなどがあれば上腹部痛などが生じることがあります。胃潰瘍の施術過程と潰瘍をともなう早期胃がんとの鑑別が必要です。内視鏡検査を受けてください☆
○粘膜不整
通常は見られない粘膜の凹凸像です。無症状ですが、潰瘍などが原因であれば、上腹部痛などが生じることがあります。潰瘍と胃がんとの鑑別が必要です。
内視鏡検査を受けてください。
○バリウム班
なんらかの原因で凹んだ部分にバリウムがたまって観察されます。これをバリウム班といいます。無症状です。原因によってその後の状態は異なります。疑われる病変が何であるかによって内視鏡検査が必要となることがあります。
○腹部石灰化
胆石、腎臓結石、リンパ節などに石灰、カルシウムが沈着したものです。
○辺縁不整
ポリープなどによって、その陰影の辺縁が不整にみられることです。無症状です。原因によってその後の状態は異なります。良性であれば通常は辺縁は整っています。しかし、悪性所見がうたがわれると、辺録が不整になります。内視鏡検査を受けてください。
○変形
潰瘍や腫瘍が大きい場合、通常の胃の形状を維持できないため、変形がみられます。過去の病変の名残りの場合もあります。病変によって食欲不振や吐き気、嘔吐、体重減少、便が黒くなるなどが見られます。進行がんの可能性があるため、早期にに内視鏡検査を受けてください。
○ポリープ
粘膜が腫瘍性に増殖して隆起している状態です。無症状です。大きさや性状によって異なります。小さいものは数mmで辺録も整っていることが多いです。大きなものや辺録が不整のもの、しだいに大きくなるものは内視鏡検査が必要です。