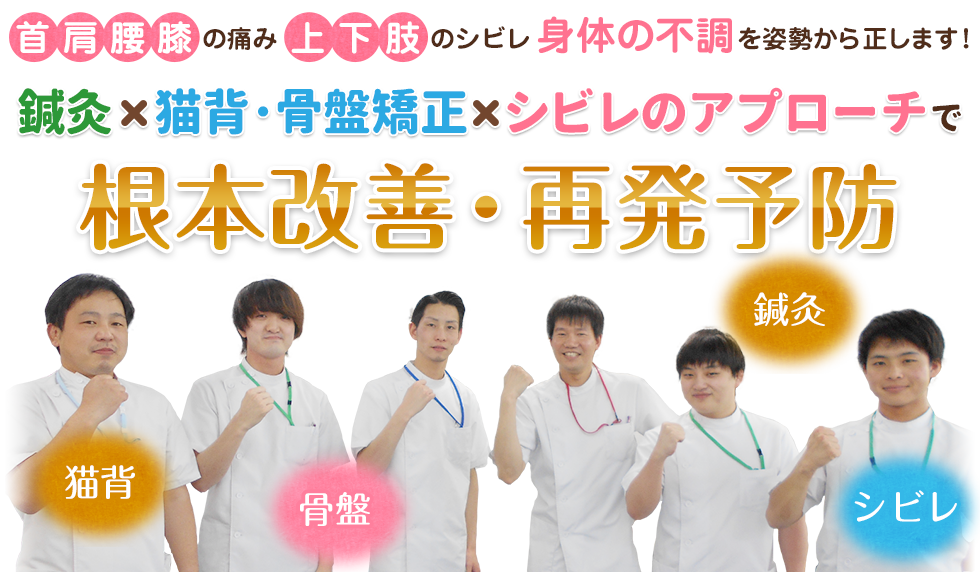
今回は上腹部超音波検査について紹介したいと思います(^◇^)
○超音波検査とは
エコー検査とも呼びます。膵臓を調べる場合は腹部超音波の一種となります。
○この検査でわかること
膵臓の形状的な異常を体に負担をかけることなく画像化して調べることができます。しかし、膵臓は体の奥のほうにある臓器なので、その異常を調べるのはなかなか困難なのが実状です。
とくに、太っていたり、腸にガスがたまっていたりすると膵臓全体の観察ができません。上腹部CT・MRI検査なども同様に活用されています。
○異常はこんな形で現われる
膵石エコー像が見られれば慢性膵炎が考えられます。悪性腫瘍があれば、その部分が腫れていたり、まだら模様として映しだされます。
○関連検査
血清膵アミラーゼ、尿アミラーゼ
○精密検査が必要な場合
上腹部CT・MRI検査、ERCP.MRCP検査、腹部血管造影検査
○ドクターズアドバイス
超音波検査装置は、CTやMRIなどに比べてずっと簡便な装置であるため、個人医院なども含めて広く活用されています。
検査方法も簡便で、しかも検査能力が高いということで、超音波検査装置は「目で見る聴診器」などともよばれています。
今回は、リパーゼについて紹介したいと思います(^◇^)
○リパーゼとは
リパーゼは、膵臓の細胞で合成される酵素で中性脂肪を脂肪は、分解されることで腸管から吸収できるようになります。
○この検査でわかること
膵臓の細胞が障害を受けたり、破壊されると膵腺房細胞で合成されるリパーゼが血液中に流出する量が増えます。膵炎などの膵臓の病気を調べる重要な検査となっています。急性膵炎では、激しい腹痛、背部痛とともに、リパーゼの値が基準に数倍になっています。慢性膵炎やすい臓癌、膵のう胞でも上昇しますが、その程度は2~3倍にとどまります。しかし、急性膵炎のように1~2週間の上昇はなく、異常値が持続することが特徴です。また、肝臓の病気でも経度の上昇がみられ、腎不全のために尿からの排泄が低下すると、持続的に高値を示します。
○基準値の範囲
検査方法により、施設によって多少ことなりますが、12~50U/Lが基準範囲です。
○要注意と危険な数値
腹痛、背部痛があり、500U/L以上では急性膵炎、慢性膵炎の悪化が考えられます。慢性膵炎が長期化すると、膵炎が荒廃しリパーゼが分泌されなくなり低値を示すようになります。
○ドクターズアドバイス
性膵炎時にはリパーゼに比べ、膵アミラーゼの方が早期に高値を示します。異常を示す期間はリパーゼの方が長いという特徴があります。また、以前は尿アミラーゼも測定されていましたが、血中膵アミラーゼやリパーゼのほうが有用性が高いため、現在ではあまり使用されなくなっています。
今回は膵臓の働きを紹介したいと思います(^◇^)
○膵臓は体の奥の方で、2つの大役を担ってる
膵臓は、長さ10~15cmほどの臓器で、胃と十二指腸に囲まれるようなかっこうで位置しています。そして、栄養素を分解する各種の消化液を分泌するため、膵管が十二指腸のファーター乳頭という出口へと通じています。
膵臓全体は、十二指腸に近い方から順に、頭部、体部、尾部というように分類されていますが、外見上は、はっきりとそのようにわかれているわけではありません。
膵臓はそれほど大きな臓器ではありませんが、じつにさまざまな役割を果たしています。その役割は、外分泌機能と内分泌機能に大別されます。
○栄養素を分解する酵素やインスリンなどのホルモンを分泌する
主な外分泌機能は、消化酵素などの十二指腸への分泌です。分泌される消化酵素は、
①炭水化物分解酵素
②たんぱく質分解酵素
③脂質分解酵素
三大栄養素と呼ばれる炭水化物、たんぱく質、脂質のすべての消化にかかわる物質を分泌しているということになります。
内分泌機能は、膵臓内に無数に分布する、ランゲルハンス島という組織が担っています。ここのα細胞からは血糖値を上昇させるグルカゴンというホルモンが、またβ細胞からは血糖値を低下させるインスリンというホルモンが、それぞれ分泌されています。
血糖値の維持、調整は、私たちの生命維持や活動エネルギーの代謝に直結するもので、栄養素の消化にかかわるのと同等の重要性をもっています。
今回は膵臓の超音波検査の判定につかわれる用語の意味を紹介したいと思います(^◇^)
○急性膵炎
膵臓の組織が急激に破壊された状態です。膵臓が分泌している消化酵素が自らの組織を消化してしまう現象で、多量の飲酒や脂肪の多い食事をした後に起こるケースがあります。
○限局性腫大
膵臓の一部が腫れているものです。膵臓腫瘤や慢性肝炎などがあるとみられる症状です。
○膵管拡張
膵臓でつくられた膵液が流れる膵管が拡張することです。正常では2mm以下ですので、確認も困難です。管の周囲の病変があると、その末梢側が拡張することが多く、原因としては、膵石や腫瘍、自己免疫性膵炎などがあります。膵石の場合、慢性膵炎も合併しやすくなりますので、精密検査が必要です。
○膵石
膵臓内でできた結石です。慢性膵炎を合併していることが多く、その原因の多くは過量飲酒です。強い腹痛や背部痛を認めることがあります。膵炎を繰り返す場合には、内視鏡的に膵管内にチューブを入れたり、体外衝撃波で結石を破砕したりするほか、開腹手術で膵臓を一部切除して膵液の流れをよくする施術があります。低脂肪が原則で、禁酒も必要です。
○膵臓壊死
膵臓でつくられている酵素が、自らの細胞に作用して壊死を生じるものです。急性膵炎がこじれた場合などに起こります。重症になると、きわめて危険な状態になります。急性壊死性膵炎ともいいます。
○膵臓腫瘤
膵臓にできた腫瘍のことです。腫瘍が良性が悪性かを診断するための精密検査が必要です。