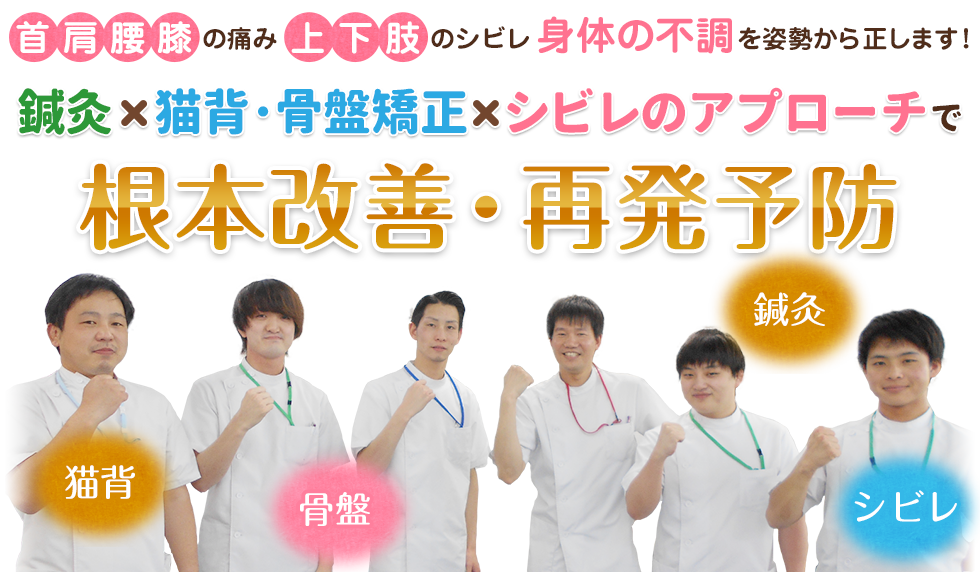
今回は、胃・十二指腸潰瘍について紹介したいと思います(^-^)
<症状>
みぞおちのあたり、に、焼けるような差しこむような、シクシクする痛みがあり、空腹時にはひどく感じられます。食後にも胸やけや、すっぱい味を感じるゲップが出る、ということがあり、さらにひどくなると吐血したり、血便がでることもあります。精神的ストレスが原因で悪化する例も多くみられる病気です。
<施術のポイント>
潰瘍そのものの施術は専門医の処置を受け、ツボ療法では潰瘍にともなう症状の暖和と心身のリラックスを促すようにします。まずは胃の機能を整えるために、かくゆなど、消化器系の機能促進に有効な背中と腹部の各ツボを指圧します。足の三里、陽陵泉、三陰交、れいだ、手の内閣なども、胃腸の調子を整えます。
痛みをやわらげるには手の合谷、全身をリラックスを促すようにします。まずは胃の機能を整えるために、かくゆ、盲yなど、消化器系の機能促進に有効な背中と腹部の各ツボを指圧します。足の三里、陽陵泉、三陰交、れいだ、手の内関なども、胃腸の調子を整えます。痛みをやわらげるには手の合谷、全身をリラックスさせるには腰の腎ゆが効果的です。
<施術のすすめ方>
○盲ゆ
腹部のマッサージと併用して消化器系の機能を高める
<位置>
おへその両脇で、おへそより指幅1本分外側
<施術>
施術者はお客を仰向けに寝かせ、両手の中指で左右のツボを同時に押す。みぞおちからおへそまでと、おへその周囲の各ツボも同様に指圧し、やさしくマッサージすれば、徐々に消化器系の機能が高まる
○かくゆ
潰瘍の原因となる胃液の余分な分泌を調整
<位置>
肩甲骨の下寄りの内側で、背骨をはさんだ両側のあたり
<施術>
お客の背中に両手をつき、左右のツボを親指の腹で小さな円を描くように押す。このツボは胃液の分泌を調整する効果がある。大腸ゆまでの各ツボも上から順に同じように指圧すると消化機能が促進されるようです。
○れいだ
みぞおちの重苦しさやむかむかした感じに効果
<位置>
足の第2指のつめのきわ
<施術>
両足の指を、爪のつけ根をつまむようにしてグリグリともみ押す。このツボは胃の症状に効果があり、みぞおちの重苦しさや、ムカムカした感じをやわらげる。胃液の分泌過剰をおさえるのに効果的です。
今回はピロリ菌検査について紹介したいと思います(*^_^*)
○ピロリ菌検査とは
ピロリ菌は胃粘膜に感染する細菌で、急性胃炎、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんなどと関係することが分かっています。正式名称は、ヘリコバクタ・ピロリ菌です。
○この検査でわかること
検査には、内視鏡検査で胃粘膜を採取して細菌の存在を確かめる方法と、呼気、血液、尿、便などから調べる方法とがあります。
呼気・便からはからはこれまでにピロリ菌に感染したかが検査できます。
また、併せてペプシノゲン検査を行うと、慢性胃炎や委縮性胃炎の進行が判別できます。
陰性であれば、ピロリ菌に感染していません。陽性で胃・十二指腸潰瘍があれば、抗菌薬などによる除菌施術の対象になります。胃炎には健康保険が利用できません。
なお、抗菌薬などでピロリ菌の除菌施術をしても、尿・血液を検体とした場合は陽性状態が続くことがあります。この場合は、呼気ガス検査か便検査で消失したかどうかを判定する必要があります。
○ドクターズアドバイス
ペプシノゲン検査とは、慢性胃炎の補助診断である血液検査です。これは胃がんのリスク診断にも利用されています。ペプシノゲン検査ではⅠとⅡがあり、Ⅰ/Ⅱの比率が低いほど、ピロリ菌感染が疑われます。なお2015年時点では健康保険が適用されていません。
今回も引き続き、消化管の診断につかわれる用語の意味を紹介したいと思います(^-^)
○胃ポリープ
胃粘膜が局所的に隆起したものです。とくに症状は起きません
○胃隆起性病変
胃粘膜が隆起した状態で、無症状です。原因によってその後の状態は異なります。大きさにもよりますが、内視鏡検査が必要となることがあります。隆起した病変は何か、そしてそれは良性か悪性かを鑑別する必要があるためです。
○急性胃粘膜病変
薬剤、ストレス、飲酒、ピロリ菌などにより急性に、胃粘膜表面がただれた状態をいいます。
○条件不良
前日遅くに食べた食べ物が胃内に残り、写真が鮮明に映らないことです。
○ばく状胃
胃の上部が後方に垂れ下がった形状をしています。
○びらん性胃炎
胃粘膜の軽度の欠損により、ただれている状態です。胃痛や胃もたれなどの症状がある方もいます。粘膜の欠損が深くなると、潰瘍となります。暴飲暴食を控えてください。症状がある場合は、、飲み薬による施術を行います。早期がんかどうかの鑑別が必要なときは、病理組織検査を行います。
○慢性胃炎
胃粘膜に炎症が起きている状態。
○十二指腸潰瘍
十二指腸粘膜の深い粘膜欠損です。無症状のものもあれば、上腹部痛のあるものもあります。潰瘍が深いとそこから出血し、便が黒くなったり、貧血などが生じます。食事はやわらかいものにします。入院施術や輸血、手術が必要になる重症の潰瘍もあります。軽症であれば薬物施術で改善します。内視鏡検査をうけてください。潰瘍の程度の判定が必要です。薬物施術ですむものが多いですが、内視鏡的止血術が行われることがあります。ピロリ菌に感染して生じていることが多く、薬による除菌施術が必要に7なことが多いです。
今回も引き続き、消化管の診断につかわれる用語の意味を紹介したいと思います(^-^)
○逆流性食道炎
胃液の食道へ逆流により、食道粘膜が傷害された状態です。内視鏡検査により、次の6つに分類されます。
①内視鏡的に変化を認めないもの
②長径が5mmを超えない粘膜障害のあるもの
③色調変化型
④少なくとも1か所の粘膜障害の長径が5mm以上あり、それぞれ別の粘膜ひだ上に存在する粘膜障害がお互いに連続していないもの
⑤少なくとも1か所の粘膜障害は2条以上の粘膜ひだに連続してひろがっているが、全周の3/4を超えないもの
⑥全周の3/4以上にわたる粘膜障害
○食道アカラシア
食道と胃の接合部の筋肉の過度の収縮状態をいいます。筋肉の異常ですので、改善は見られません。内視鏡では診断がつかないことも多いのですが、上部消化器X線検査で診断が可能です。通過障害がひどくなると、食べ物が飲み込みにくくなる、吐いてしまうといった症状が徐々に悪化します。一回の食事の量は少なめにし、時間をかけて食べてください。内服薬で症状を改善させる方法や、内視鏡的に狭い部分を拡張させる方法がありますが、一時的なことが多いので手術を行うことが多いです。
○食道炎
カビ、薬剤、胃液の逆流などにより、食道粘膜が赤くただれた病変です。
○食道外腫瘍
食道壁周囲の気管支などの臓器より発生した腫瘍です。
○食道拡張
通過障害により、その口側が拡張することです。通過障害がひどくなると食べ物を飲み込みにくくなる、吐いてしまうという症状が徐々に悪化します。通過障害の原因が、がんであることもありますので、内視鏡検査が必要となることがあります。外部からの圧排であれば、それを確認するためにCTなどの追加検査が必要です。
○食道憩室
食道の壁が部分的に外側へ袋状に突出したものです。
○食道腫瘍
食道の一部が増殖し、内部に突出、もしくは変形している状態です。通過障害があると、吐き気、嘔吐や食べ物が飲み込みにくいなどの症状が現れます。内視鏡検査で腫瘍の状態や、良性か悪性かを検索する必要があります。
今回も引き続き消化器の診断につかわれる用語の意味について、紹介したいと思います(^-^)
○胃液食道逆流
食道裂孔ヘルニアなどにより、食道下部に胃液が逆流する現象です。
○胃外性腫瘤
胃の外側に発生した腫瘤により、胃が圧迫される所見です。
○胃潰瘍
粘膜欠損が深いものを言います。無症状のものもあれば、上腹部痛のあるものもあります。出血をともなうと黒色の便が出現し、貧血の原因になります。食事はやわらかいものにします。入院施術や輸血、手術が必要になる重傷の潰瘍もあります。軽症であれば薬物施術で改善します。内視鏡(胃カメラ)検査を受けて潰瘍の程度を判定することが必要で、それによって施術方針がことなります。薬物施術ですむものが多いですが、内視鏡的止血術が行われることもあります。
○胃潰瘍瘢痕
過去に発症した胃潰瘍の跡で、無症状です。内視鏡検査が必要なことがあります。早期胃がんとの鑑別が必要です。病理組織検査を行うことがあります。ピロリ菌に感染していなければ、再発予防のために除菌施術を行います。
○胃下垂
胃が骨盤より下の位置にある症状です。
○胃陥凹性病変
正常の胃粘膜が一部欠損した病変のことです。腫瘍、潰瘍などで見られます。
○胃憩室
胃壁の一部が外側へ袋状に突出したものです。無病状であり、放置してかまいません。
上部消化管X線バリウム検査とは
造影剤のバリウム液を口から飲んで、食道から胃、十二指腸までをX線モニターに消化管の形や内腔を映し出します。
この検査でわかること
胃や食道、十二指腸の表面にバリウム液が薄く付着することにより、X線写真で表面の凸凹の変化が白黒の濃淡となって映ります。これにより、食道、胃、十二指腸のポリープ、潰瘍やがんなどが発見できます。
異常はこんな形で現れる
正常な場合は全体が均一に白い映像として描かれます。粘膜面に凹凸があるとバリウムの「抜け」や「たまり」として現れ、潰瘍は「くぼみ」として現れます。がんは「くぼみ」や「盛り上がった画像」として映ります。
関連検査
ピロリ菌
精密検査が必要な場合
検査で上部消化管の潰瘍やがnなどが疑われた場合は、上部消化管内視鏡検査を行います。
ドクターからのアドバイス
検査当日は胃を空にしておく必要があり、原則的には前日の夜9時以降は飲食を避けます。検査終了後は、下剤を服用し、水分を多くとって、バリウムが腸に残らないようにします。
バリウムは、検査後1~2日以内に白いベンとなります。